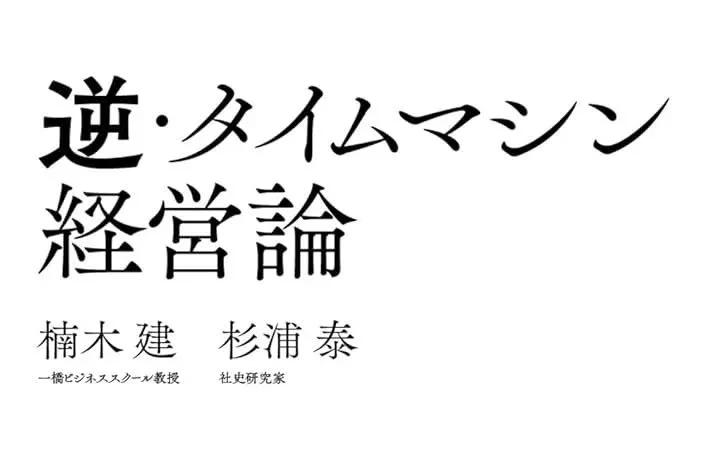『逆・タイムマシン経営論』に学ぶパーパス経営の本質 ──非合理こそが競争優位になる理由
こんにちは。パーパス・ブランディング・コンサルタントの小西です。
先日登壇した『CXフォーラム2025』(主催:東洋経済新報社・ラーニングイット*1)で、鼎談させていただいた楠木建先生(⼀橋ビジネススクール特任教授)のご著書『逆・タイムマシン経営論』を改めて読み直しました。そこで感じたのは、先生のお話と、私が常々提唱している「パーパスブランディング」という考え方に、驚くほどの整合性があるということでした。
今回は、楠木先生のご著書から「そもそも経営において、どんな考え方が重要なのか?」という視点でお話ししたいと思います。
*1:「CXフォーラム2025」https://toyokeizai.net/sp/sm/cx2025/
楠木先生の視点とパーパスの関係
今回のフォーラムでは、「企業のCX(顧客体験)向上」について基調講演をさせていただいた後、楠木建先生、株式会社ラーニングイットの畑中伸介社長と鼎談の機会をいただきました。
印象に残っているのは、楠木先生の著書『逆・タイムマシン経営論』にまつわるお話です。この本では、「未来から見た視点ではなく、歴史から今を見直すこと」の重要性が説かれているのですが、これが実は、私が日々ご支援しているパーパス経営やパーパスブランディングの本質と重なる部分がとても多かったのです。
経営における「非合理」の追求こそが、競争優位の源泉
楠木先生とのお話で私が特に興味深かったのが、「儲け続けるには、戦略を他社に模倣されるのを防ぐ障壁が必要だが、より有効なのは「業界の常識に反し、他社が模倣を忌避するような戦略だ」とする。そうした戦略は、一見すると非合理だが、ストーリー全体では合理性があるとして「核心は非合理の中の理にある」」という内容でした 。
一見すると非合理的に映ることも、自分たちの「パーパス(存在意義)」から逆算すると、実は長期的にやり続けるべきことである、と仰っています。この言葉を聞いたとき、私はまさに「パーパス経営」の本質を見た気がしました。
アマゾンを例に出すと、「地球上で最もお客様を大切にする」ことを企業理念に掲げるアマゾンのEC機能の中には、「リマインド」という以前購入した商品ページにアクセスすると、「〇年〇月に購入」と表示されるものがあります 。私自身、「また同じ本を2冊買うところだった」という、経験がしばしばあるのですが、この機能のおかげで何度も助けられています。
しかし、当時の株主からは「なぜそんなことをするのか?間違えた顧客が悪いのだからわざわざ自分たちの売上に繋がらない機能は無駄だ」という意見がありました。
ですがアマゾンでは、お客様の信頼を長期的に獲得するためには、お客様に「この顧客体験最悪だった」と思わせることの方が、自社にとって多大で長期的な損失だと考えているのです。だからこそ、一見非合理的に見えるリマインド機能も、アマゾンのパーパスから考えると、やり続けるべきことなのです 。
「飛び道具トラップ」に陥るな
先生の著書の中で、先生は「企業はいろんなトラップにはまってしまう危険性がある」と指摘されており、その一つを「飛び道具トラップ」と称していました。
「飛び道具トラップ」については是非先生の著書でご確認いただければと思いますが、そこで指摘されているのは、「他社がやっている最新の取り組みを、そのまま取り入れることの危険性」です。今話題の手法やビジネスモデルを“未来の正解”だと誤認し、文脈を無視して導入してしまう企業が少なくないかもしれません。
例えば、「これからは生成AIだ!これで一儲けできるかもしれない」という発想です。楠木先生曰く、このような飛び道具的な発想が、本当に自分たちの経営戦略の文脈に当てはまるのか?本当に必要なものであれば使うべきですが、飛び道具が先行して「AIを使って”何か”やる」という発想ではなく、自分たちの文脈に本当に合っているかどうかをしっかり判断して使うべきだと指摘されています。
ポーター賞とパーパス経営の関係性
ここで楠木先生が関わっている「ポーター賞」(*2)についてもご紹介したいと思います 。これは、ハーバード大学のマイケル・E・ポーター教授に由来した、優れた経営手腕や独自性のある戦略で高い収益性を達成した企業を表彰したビジネス賞です。
このポーター賞で受賞された企業を見てみると、必ずしも最先端な”何か”を使った企業ではありません。ポーター賞は単なる「成果が出ている会社」ではなく、戦略の原理原則を体現している企業を評価しているようですが、受賞企業の多くは、自社のパーパスから逆算して、自分たちの大切なステークホルダーに対してどうあるべきか、どのようにステークホルダーの課題を解決するかを、とことん突き詰めている会社が多いことが分かります。
*2:Porter Prize(https://www.porterprize.org/index.html )
非合理を貫き、顧客の課題解決を追求する「ミルボン」の事例
私が以前長期にわたりサポートさせていただいた美容室向けのヘアケア製品を製造・販売する化粧品メーカー、株式会社ミルボンも2020年にポーター賞(*3)を受賞しています。
ミルボン社は、自分たちのパーパスを「ヘアデザイナーを通じて、美しい生き方を応援する事業展開をします。」としており、常にヘアデザイナー(美容室)が、顧客満足度を高め継続した成長ができるかをサポートしています。
ミルボン社には「フィールドパーソン」という仕組みがあります。フィールドパーソンの役割は、美容室で製品を取り扱っていただくことがゴールとするのではなく、“いかに美容室の繁栄に貢献できるか?”を考えた活動に徹することです。
この考えをもとに、一軒一軒異なる美容室の課題やオーナーの想いと向き合う中で、美容師向けの販売スキルを高めるための講習の実施、店内会議への参加、店舗の年間スケジュールや販促計画の立案、さらには美容室の経営計画づくりまでほぼ無償で幅広い支援を行っています。ミルボン社の株主からは「金の無駄だから、製品の販売をもっと強化した方がいい」と指摘されるかもしれませんが、ミルボン社はこの一見「非合理」に思える顧客支援で成功し、成長してきた会社なのです。「フィールドパーソン」のような支援を続けてきた結果として、ステークホルダーからミルボン製品も信用され、支持され続けています。
一見合理的でないことも、自分たちの会社にとって顧客の課題を解決するためにすべきことが自分たちの意義(パーパス)である。それをやり続けられる会社が、「他社と一線を画して自分たちの存在価値を作り、競争力を持って成長できる」と楠木先生は仰っています。これこそが、まさにパーパス経営の本質だと私も強く感じています。
*3:ポーター賞受賞企業「株式会社ミルボン」https://www.porterprize.org/pastwinner/2020/12/07130000.html
「マクロへのすり替え」
もう一つ、楠木先生が著書の中で警鐘を鳴らしている印象的なポイントは「マクロへのすり替え」です 。これは「外部環境のせいにしてはいけない」ということです。マクロな問題ほど人々は他責志向に陥りやすい傾向にあります。失敗を人のせいにしたり、安易に外部環境を理由にしてしまうのは、自社の「在り方」にコミットしていないからだと、楠木先生は著書で仰っています 。
他責志向に陥らずチャンスにしたアイリスオーヤマ
ポーター賞も受賞しているアイリスオーヤマ株式会社の代表取締役会長である大山健太郎氏は「ピンチはチャンスではなくて、ピンチ”が”チャンス」と、まさに企業のあるべき姿を端的に表しています。コロナ禍だからこそチャンス、コロナ禍だからこそ自分たちのステークホルダーの困りごとが一層明確になる。ならばそこに対して、自社なりにソリューションを考えれば、お客様も喜んでくれて、自分たちにとってもチャンスになって成功・成長できる、という考え方です。
パーパス経営を実践していく上で、この「飛び道具トラップ」と「マクロへのすり替え」は、多くの企業が陥りやすい罠であり、自社らしさを見失ってしまうきっかけになっているのではないかと感じています。
パーパスは「つくる」ものではなく、「見出す」もの
パーパスとは、「企業がなぜ存在しているのか」「社会にどんな意味を持つのか」を、社内外に問い直し、言語化し、発信していく営みです。そしてそれは、“未来を予測してつくる”ものではなく、“過去と今に宿る意味を発掘する”ものといえます。
そういう意味で、楠木先生の「未来から考えるのではなく、歴史の積み重ねを軸に考えるべき」という視点は、パーパスブランディングに取り組むすべての企業にとってヒントになるのではないでしょうか。
『逆・タイムマシン経営論』が教えてくれること
楠木先生の『逆・タイムマシン経営論』は、まさにこのような「非合理」とも思える経営判断や、自社の軸をぶらさずに事業を推進していくことの重要性を、分かりやすく、またユーモアも交えながら解説している本です。
皆様にも、是非『逆・タイムマシン経営論』を読んでいただき、貴社のパーパス経営、そしてパーパスブランディングをさらに深めるヒントを見つけていただければ幸いです。
AStoryでは、企業のパーパス設計から社内浸透、パーパス・ブランディングによる対外発信まで、一貫したサポートを提供しています。
貴社が「深いパーパス型」へ進化するための第一歩を、AStoryと一緒に踏み出しませんか?
AStoryではアマゾンジャパンの黎明期からトヨタやGoogleを抜いてトップブランドとなった実績(「総合ランキングは、「Amazon.co.jp」が初の総合首位を獲得」)をもとに、ベンチャー、スタートアップ企業の新規上場におけるPR戦略立案やPR担当者育成のサポート、パーパスブランディングの構築支援をしています。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。